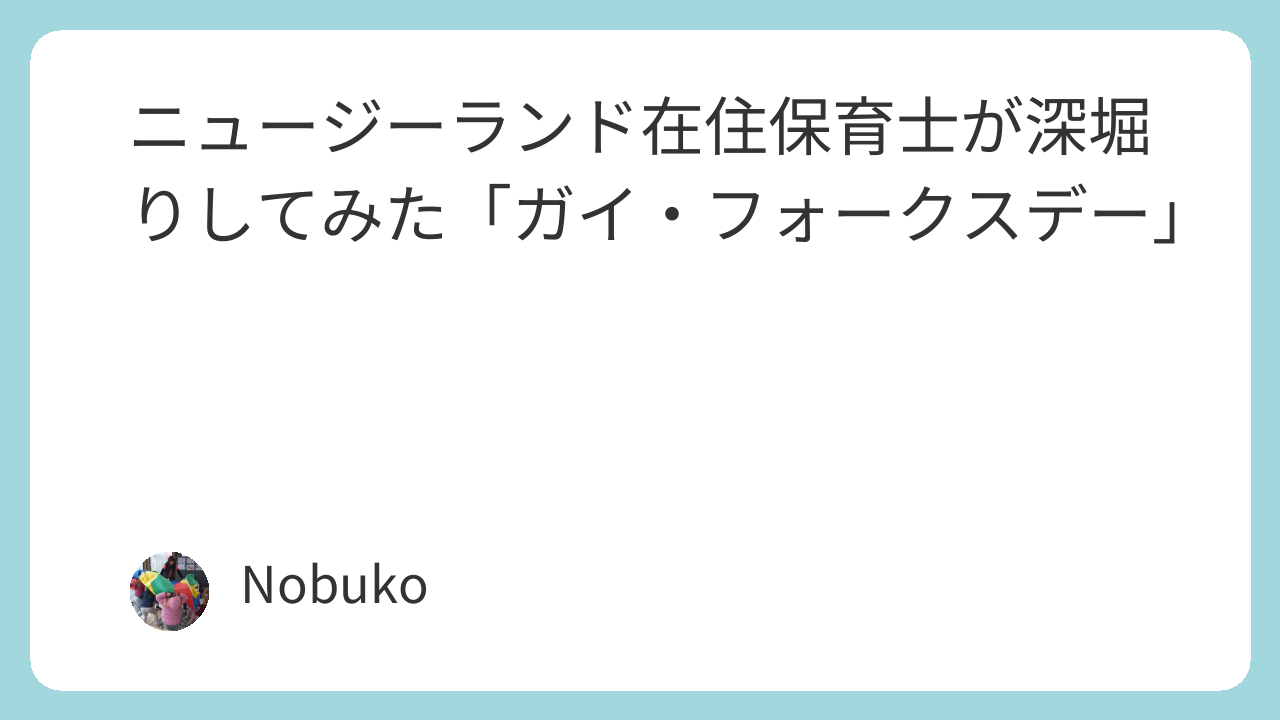こんにちは。ニュージーランドで保育士をしているNobukoです。
今日は、11月になると街のあちこちで聞こえてくる「パーン!」という花火の音――
そう、「ガイ・フォークス(Guy Fawkes)」についてお話ししたいと思います。
移住・ワーキングホリデー・駐在などでニュージーランドに来られたばかりの方にとっては、「なんで突然花火?」「どういう由来?」と疑問に思われる方も多いこのイベント。私自身、移住前は全く知りませんでした。
この記事では、保育の現場での体験を交えながら、ガイ・フォークス・デーの歴史、ニュージーランドにおける過ごし方、そして子どもたちとどう関わるか、という視点でゆっくりとご紹介します。ぜひ、どうぞ気軽に読んでください。
ガイ・フォークスって何?
「Remember, remember the fifth of November」
――11月5日を忘れるな。そう始まる有名な言葉を聞いたことがあるでしょうか。
実はこの「ガイ・フォークスデー」イギリスではじまり、ニュージーランドなど英国連邦国ではよく知られたイベント。
1605年「火薬陰謀事件(Gunpowder Plot)」をきっかけに生まれた記念日です。
当時、イギリスのジェームズ1世に対してカトリック教徒たちが反乱を企て、
国会議事堂を爆破しようとしました。その中心人物が、ガイ・フォークス。
彼は発見され、処刑されましたが、その事件を防げたことを喜び、
国王の無事、この「クーデターが失敗に終わった」ことを受けて、イギリスでは「11月5日は事件を忘れまい」という意味で、花火と焚火(bonfire)を用いたお祝いが始まりました
ニュージーランドではどう祝うの?
ニュージーランドでは “ガイ・フォークス・デー” と呼ばれ、花火が解禁される日とされています。実際には、花火販売や使用が11月2日から5日までの4日間に限られており、18歳以上という条件や購入時の身分証明というルールもあります。
移住してきた当初、私は「線香花火で締める日本の花火文化」がごく当たり前だと思っていました。ところがニュージーランドでは、線香花火のようなものはなく、“スパークル(手持ち花火)”が主流。それを見て、思わず「こんな風なんだ…」と日本との違い感じたことを覚えています。
夜暗くなり、どこからか花火の音が聞こえてくる――そんな11月初旬。私自身、日本で育った “花火=夏の風物詩” という感覚とともに、ここでの“秋から初夏への移り変わり”の途中に感じるこのイベントを、「新しい季節の合図」でもあると感じるようになりました。
街のスーパーマーケットでは、ガイ・フォークスの数日前になると
花火がずらりと並びます。
普段は販売されていないので大人も子どもも、日本と比べてものすごく高いお値段ですが、買って楽しむKiwi(NZ人)たち。
家族や友人たちが集まり、庭や公園でバーベキューをしながら花火を楽しむ姿が見られます。
保育園でのガイ・フォークス体験
私が働いていたモンテッソーリ園では、イギリス出身のセンターマネージャーが毎年
「子どもたちにもガイ・フォークスを体験してもらおう」とイベント実施していました。
そのときに印象的だったのが、彼女が子どもたちと一緒に歌ってくれた曲――
「Remember, remember the fifth of November」マザーグースのように節をつけた語り口が忘れられません。
英語の歌詞には「ガイ・フォークス」「火薬」「裏切り」といった言葉が出てきますが、子どもたちにはもちろん難しい。
そこで私たちは、歌を“怖い話”ではなく“歴史の出来事”として伝え、
「昔、イギリスでこんなことがあったんだよ」と
絵本や紙芝居を使って紹介しました。
子どもたちはちょっと怖い絵柄も静かに聞いていましたが、火薬陰謀事件そのものよりも、
お話しの最後に「みんなで花火をして祝います」という部分に興味津々。
このお話しを読みおえたら、みんなで園庭でスパークル花火をします。
円になって自分の花火が点火されるのを待つ子供たち。
点火されるとお顔がにこやかに。
文化の違いを感じながらも、
「どの国でも、光や音を楽しむ気持ちは同じなんだな」と思う瞬間でした。
保育士・教育現場から見えてくるもの
私が保育園で感じたのは、このイベントを通じて「文化的背景を知る」「異文化を受け入れる」機会が生まれるということです。
例えば、歌の中にある “Gunpowder, treason and plot(火薬、反逆、そして陰謀)” という言葉は、子どもたちには難しすぎるかもしれません。でも、その背後に「昔、こんな出来事があった」というお話を、絵本や紙芝居、そして実際に手持ち花火を体験することで、「楽しむ時間」として子ども自身が捉えられるようになります。
また、手持ち花火という小さな体験を通じて、ルールや安全、そして終わった後の処理(バケツの水へ入れる)までを自分たちで行うことで、子どもたちが「参加している」という実体験を持てるのも大切なことです。
こういう日々の小さな体験が、私自身「異国で暮らすということは、こういう小さな違いを知ることなんだな」と実感する瞬間でした。
ガイ・フォークスデーの変遷
かつては「ガイ・フォークス人形(ガイ)」を作って燃やし、
「A penny for the Guy(ガイにおめぐみを~)」と子どもたちが声を上げて歩く――
そんな風景がイギリスではよく見られました。
しかし近年では、そうした伝統的な風習は減少傾向にあります。
代わりに、地域の花火大会や公園でのライトショーが人気。
家族で安全に楽しめるイベントへと変化しているのです。
ニュージーランドでも同様に、
個人の花火よりもコミュニティイベントが重視されるようになっています。
特にオークランドやウェリントンでは、
環境への配慮から公的な花火大会を廃止する自治体も出てきています。
【深堀】小説『ガイ・フォークス』
イギリスの作家ウィリアム・ハリソン・エインズワースによる小説『ガイ・フォークス』では、
実際の陰謀事件をもとに、信仰と忠誠、裏切りと理想の狭間で揺れる人間の姿が描かれています。
この作品では、ガイ・フォークスは単なる「反逆者」ではなく、
信念を持ち、信仰のために立ち上がった人物として描かれています。
歴史の教科書で見る彼の姿とは少し違い、
人間味のある“ひとりの男”として描かれるところに、昔も共感され人気が出たのでしょう。
【深堀】映画『V for Vendetta』と現代のガイ・フォークス
そして現代で「ガイ・フォークス」と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、
映画『V for Vendetta』
仮面をかぶった主人公「V」は、
抑圧された社会に対して自由と正義を求めて立ち上がります。
彼のかぶる“ガイ・フォークスの仮面”は、
今では世界中の抗議運動や社会運動の象徴にもなりました。
このガイフォークスマスク、コロナワクチン強制命令が出た2021年、目にする機会が多かったのですが、映画の設定年が2020-2021年を設定というのも興味深いです。デジタルID、ロックダウン・・・こんなあらすじが2006年にリリースされていたなんて。必然か、偶然か。
V For Vendetta は警告だった、私たちは試されている
ガイ・フォークスは、
400年以上の時を経て“反逆者”から“自由の象徴”へと意味を変えたのです。
その変化は、人々が何に希望を見出すか――という心の動きを映しているように感じます。
まとめ
ガイ・フォークスデーは、単なる花火の日ではありません。
かつてのクーデター・反乱事件から生まれた記念日が、
今では「家族で光を楽しむ日」や「自由を思い出す日」へと変化しています。
ガイ・フォークスの夜――
それは、過去と現在、そして歴史・文化、人の心理について考える日でもあります。